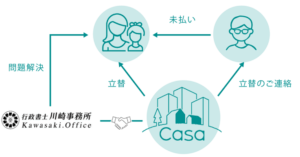はじめに
日本人と外国籍の配偶者による国際結婚では、文化や法律の違いから将来的なトラブルが生じる可能性があります。こうしたリスクに備える手段として注目されているのが「婚前契約書(プレナップ)」です。婚前契約書とは、結婚前に夫婦となる二人が結婚後の生活上のルールや、万一離婚に至った場合の条件を取り決めて書面に残す契約のことを指します。特に国際結婚の場合、契約書作成を専門とする行政書士の視点から見ても、結婚前にこうした取り決めを文書化しておく意義は大きいと言えます。以下では、国際結婚を前提として婚前契約書を作成する目的やポイントについて、法令解釈に誤りのないよう解説します。
1. 準拠法の明確化(どの国の法律を適用するか)
国際結婚では、夫婦に関わる事柄をどの国の法律に基づいて決めるかという問題が生じます。日本人と外国人が結婚した場合でも、日本で生活するのであれば通常は日本法が適用されます。しかし、配偶者の母国では結婚や離婚の制度が日本と大きく異なることもあり、後々「どちらの国の法律に従うのか」で争いになるケースも少なくありません。そこで婚前契約書において、準拠法(適用法)を明確に合意しておくことが重要です。例えば「夫婦間の財産分与や離婚条件について日本法を準拠法とする」「子どもの養育や親権について〇〇国の法律に基づく」等、事前にどの国のルールに従うか決めておけば、将来の紛争を避けスムーズに協議を進められるでしょう。特に今後どちらかの母国で生活する可能性がある場合には、適用法を婚前契約書で明示しておくと安心です。
2. 夫婦間の財産管理に関する取り決め
結婚生活におけるお金や財産の管理方法を明確にしておくことも、婚前契約書の重要な目的の一つです。国際結婚では経済観念の違いや資産格差が大きい場合もあるため、以下のような点を事前に話し合っておくと良いでしょう。
- 婚姻期間中の収入・費用の分担: 日常の生活費(婚姻費用)を夫婦のどちらがどの程度負担するか、共働きの場合の家計負担の方法(共同口座を使うか別会計にするか)などを決めます。日本法では夫婦に互いを扶助する義務(民法第760条)があるため、一方に過度な負担が偏ったり他方が生活費を全く負担しないという不公平が生じないよう、双方納得のうえで定めることが肝心です。また、収入や資産を互いに開示するかどうかも決めておけば、後に相手の財産状況が不明で公平な分配ができないという事態を避けられます。
- 財産の帰属と財産分与のルール: 結婚前から各自が持つ財産や、結婚後に形成した財産をどのように扱うかも重要なポイントです。日本では婚姻中に夫婦が協力して得た財産は名義に関わらず共有財産とみなされ、離婚時にはその増加分を2分の1ずつ分け合うのが原則です。しかし国によっては、結婚前の財産まで結婚後に共有とする場合や、逆に婚姻中の財産も完全に別々に管理する制度もあります。そこで婚前契約書で夫婦の財産の帰属を定めておきます。例えば「結婚前の預貯金や不動産は各自の固有財産とする」「婚姻中に取得した財産は夫婦共有とするが、持分は夫〇〇%・妻〇〇%とする」等の具体的な取り決めです。一方が会社経営者で事業資産を離婚時の財産分与対象に含めたくない場合や、夫婦間で資産額に大きな差がある場合も、こうしたルールを設けておくことで将来の争いを防ぎ、公平で納得感のある解決につなげることができます。
- 別居・離婚に備えた資産整理の方針: 将来万一別居や離婚に至った場合に備え、財産の分け方や金銭的条件について方向性を決めておくこともできます。例えば「離婚の際には解決金として○○万円を支払う」「別居時の婚姻費用は月々○○円を支払う」といった条項です。離婚が現実化していない段階の約束であるため法的拘束力は限定的ですが、あらかじめ合意があることで万一の際にもめずに済む可能性が高まります。
3. 子どもの監護・教育・宗教に関する取り決め
国際結婚では、将来子どもを授かった場合の育児方針についても意見の相違が起きやすいものです。婚前契約書の中で子どもの監護(誰が主に子どもを育てるか)や教育方針、宗教について前もって取り決めておけば、夫婦の間で認識を共有し、不要な衝突を避けることが期待できます。具体的には次のような事項が考えられます。
- 親権・監護に関する合意: 子どもが生まれた後の育児の役割分担や、万一離婚となった場合にどちらが親権・監護権を持つか、面会交流をどうするかといった方針です。婚前に「離婚時には子の親権者を妻とし、夫は定期的に面会交流を行う」など合意しておけば、いざという時の大まかな指針が双方に共有されます。ただし実際に離婚する際には子の最善の利益を優先する必要があり、契約時の取り決めどおりにならない可能性がある点には留意しましょう。
- 子どもの教育方針の共有: 子どもの教育について、どの国でどのような教育を受けさせるかといった基本方針を事前に話し合います。文化の違いから教育観が異なることも多いため、契約書に方針を残しておくと結婚後の意思決定がぶれにくくなります。
- 宗教に関する取り決め: 配偶者が特定の宗教を信仰している場合、その教義や習慣が結婚生活や子育てに影響することがあります。婚前に互いの宗教的背景について十分説明し合い、「子どもが生まれたら〇〇教の行事にも参加させる」「子の宗教は本人が判断できる年齢になるまで決めない」等の取り決めをしておくと良いでしょう。
4. 語学力や文化的誤解によるトラブル防止と情報共有
日本人と外国人のカップルでは、言葉の壁や文化の違いから思わぬ行き違いが生じることがあります。婚前契約書を作成する過程で、お互いの価値観や考え方を確認し合うことができます。日本では暗黙の了解を重んじる傾向がありますが、異文化間では何事も明確に言葉で伝えることが不可欠です。契約書という形でルールを明文化しておくことで、「言った/聞いていない」といった水掛け論を防ぎ、誤解を減らす効果があります。
また、婚前契約書は双方が理解できる言語で作成することが大前提です。日本語が不得意な相手には契約内容を母国語や共通語(英語等)に翻訳して確認し合い、必要に応じて通訳を手配します。日本の公正証書は日本語でのみ作成され法的効力を持つため、翻訳文を添付して相手にも内容を理解させる配慮が重要です。さらに、契約内容について話し合う過程で、育ってきた環境の違いや金銭感覚、家族観などについても自然と情報交換することになります。こうした情報共有により価値観のズレを事前に認識でき、結婚後の衝突を予防することにつながるでしょう。
5. 契約内容の継続的な見直しの必要性
婚前契約書は結婚時点での合意事項をまとめたものですが、結婚生活が続く中で状況は変化していくものです。したがって契約内容を定期的に見直す視点も持っておきましょう。例えば、子どもが生まれた、新たな資産を取得した、転職・退職した、海外に転居した等、大きな変化があればそれに合わせて条項を修正した方が良い場合があります。契約書に定期的な見直しを行う旨を盛り込んでおくか、数年ごとに専門家に相談して内容を現状に適合させておくと安心です。常に夫婦の実情に合うよう契約内容を更新しておくことが、契約書の実効性を保ち二人の安心にもつながります。
おわりに
婚前契約書は、国際結婚において二人が将来に向けて共通認識を持ち、トラブルを未然に防ぐための有効な手段です。しっかりと話し合い書面に残しておくことで、結婚後の生活を円滑に送ることができるでしょう。ただし契約内容は契約自由とはいえ、民法その他の強行法規や公序良俗に反する条項は無効となります。例として、一方の扶養義務を過度に制限するような取り決めは認められません。契約書を作成する際には法律上の限界を踏まえた条項設計が求められますので、専門家である行政書士に相談すると良いでしょう。国際結婚を控えた方は、本稿で挙げたポイントを参考に、将来の幸せのために婚前契約書の作成をぜひ検討してみてください。